守護霊、交代
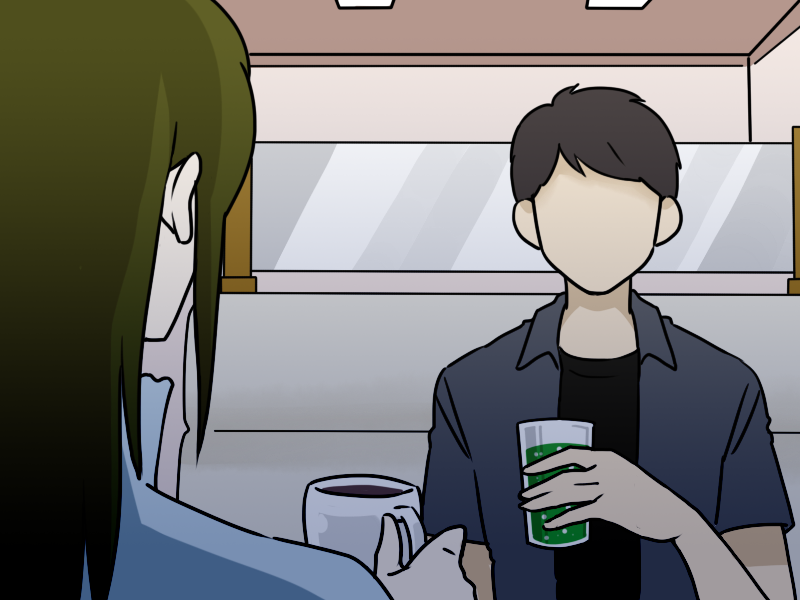
その日の最終講義であったゼミの終わり、教室から出たところでK子を呼び止めた。
「何?」
随分とそっけない返事が寄越されたが、気にせず鞄から袋を取り出しK子に渡す。
「お土産。ちょっと実家に帰ってたんだ」
墓参りをしに、とまでは言わずにおく。「そういえば先週大学来てなかったね」と言いながら袋を受け取ったK子は、その中身を覗いて小さく笑った。
「金平糖。私は君のご先祖様じゃないけど」
微かに弧を描いた目がじっと俺の後ろを見つめ、その目を丸くする。またK子には何か見えているな、と思い心の中でため息を吐き出した。するとK子が意外なことを言う。
「ご飯でもどう?」
突然の誘いに、今度はこちらが目を丸くする番だった。だけれどその驚きはあまり外に出さないようにして、「いいけど」と小さく頷くと、大学の傍にあるファミレスへと足を運んだ。
「守護霊、交代したみたいよ」
弾んだ会話をするでもなく、どちらかと言えば黙々と運ばれてきたご飯を食べ、デザートまで頼んでいたK子が、それに口をつけたところで喋った。多分これが言いたかったのだろう。
「……」
返す言葉の思い浮かばない俺にはお構いなしに、K子は言葉を続けた。
「金平糖の好きなご先祖様はもういなくて、新しい守護霊がきちんと憑いてる。これでもう危ない目に遭う心配はなさそうだけど」
一度言葉を切ったK子が僅かに目を光らせ、珍しく興味のある眼差しを向けてくる。
「たまに見えたりしてない?」
ドキッと心臓が一度大きく跳ねた。背中に嫌な汗を掻いているのを感じ、手元にあった水に手を伸ばす。一口飲むと少し気分は落ち着いた。
「今度の守護霊は前の守護霊よりも強い。すごく力のある人が憑いてる。でも性格的にはちょっと適当……放任的なところもあるみたいで、多分君はその人の影響を受け始めてる。今までの自分とは少し違った道を行くことになるかもね」
一気に言いたいことを言い終えたK子は、若干満足げな顔をしてデザートの隣に置かれたコーヒーへと手を伸ばす。少しの間流れた沈黙のあと、ため息を吐き出してから言葉を発した。
「たまに、見えているような気がする」
ご先祖様といわれる少女を見て以来、時々この世のものではないものを見るようになった。
「はっきりとじゃないけど時々、影を見るような感じで」
ホームに佇む女性だったり、ビルの下にいるスーツ姿の男性だったり。彼等はとても存在感が薄く、ともすればスウッと消えてしまいそうなのに、辺りの空気を変えそこに存在していた。最初それに気付いた時は驚きのあまり体が凍りついたけれど、知らないふりをしていれば向こうから何かしてくることはないから、なるべく気にしないようにすることにしている。
「やっぱり。霊感が強くなってる」
「……嬉しい話じゃないな」
「でしょうね。私だって見えてるのが嬉しいわけじゃないし」
表情を変えずに喋るK子だが、K子なりに苦労があったということだろうか。
「強い守護霊だから、たとえ見えたとしても霊の方から何かしてくることはないと思う。だけど、直感で危なそうだと思うものを見たら気を付けてね」
「危なそうなものって?」
それは教えておいてもらわないと、地雷を踏んだらマズい。今日のK子はやけに親切だなと思いながら尋ねた。
「実際に見たらわかる。そうそういないけど……まあ、取り敢えずは肝だめしとかで心霊スポットには行かないこと。ああいうところには結構危ないのがいるよ」
「……肝に銘じておく」
言ってから、暑くなってきた季節柄、そろそろそんなところへ行こうと言い出す奴がいそうだと思った。
「なあ、K子は見たことある?危ないやつ」
ちろりと、様子を窺うようにK子がこちらへと視線を送ってくる。
「一度だけだけど、本当に危ないのを見たことがある」
「どんなの?」
「……」
K子が僅かに眉をひそめた。あまり言いたそうではないが、続きを待ってみる。
「怨念がすごくて、成仏させることも無理だから普段は封じてあったの。姿形があったわけじゃなく、とにかくただ真っ黒だった。私はそれに憑かれたわけじゃなかったけど……影響を受けて熱も出したし、暫くひどい霊障にも悩まされた」
話を聞くだけでぞっとしたものが背筋を駆け上がる。K子が言うからには本当の話だ。そんなものがどこにいるのか、暗に尋ねてみる。
「普通に生活していたらそんなものにはそうそう出会わない。だから、普通に生きるのが大事よ」
ごちそうさま、とK子が立ち上がる。スッとレシートがこちらに差し出された。
「?」
「今日の受講料ということで。よろしく」
こんな愛嬌も振りまけるのかという笑顔が向けられ、呼び止める間もなくK子が手を振り去って行く。
「おいおい……」
こんなところで奢らされるとは、と脱力し重心を背もたれに預けたところで、テーブルに置いたままのスマホがブルッと震える。
同じゼミのA太から、「ゼミ内きもだめし決定!」と書かれたメールが届いていた。


